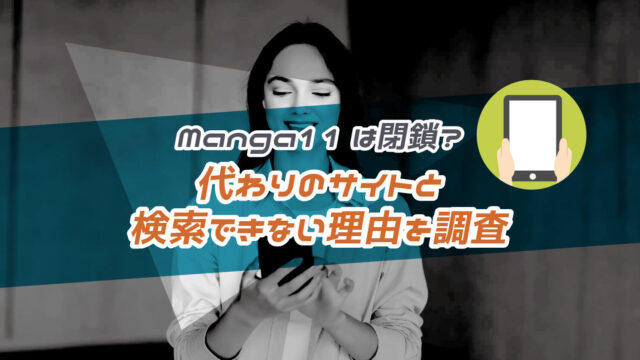「電子書籍は記憶に残りにくいの?」と気になっていませんか?
電子書籍は、紙媒体の本と比較して、紙独自の触感などがなく、使う五感が少ないから頭に入りにくいのではないかと考えている方もいます。
結論からお伝えすると、紙媒体の方が長期的な学びにとっては優位性が高いものの、使い方次第で電子書籍でも記憶に残りやすくできます。
この記事では、研究者が紙媒体の本と電子書籍を分析した研究結果などにもとづいて、電子書籍と記憶の関連性について解説していきます。
それだけではなく、記憶定着に向けた改善方法、読書術まで説明していますので、電子書籍で学ぶ効率を上げたいと考えているなら、ぜひ最後までご覧下さい。
3つの研究からわかる電子書籍だと記憶に残りにくい原因
実は、紙媒体の本とスクリーン画面で見る文字を比較した研究は1980年代から始まっています。
権威のある大学が長い研究の中で、電子書籍は、
- 「記憶に残りにくい」
- 「頭に入りにくい」
と考えられる研究結果を出しています。
「それは、どんな研究だったの?」と思われますよね?
この段落では、3つの研究からわかる電子書籍だと記憶に残りにくいと考えられる原因をご紹介します。
電子書籍は短期記憶向きである
2003年には、ケイト・ガーランド氏らが行った研究では、学生50人に教材をモニターと小冊子両方を読ませ、20分後にテストを行いました。
結果、モニターで学習した時と小冊子の時では記憶方法が違っていたのです。
モニターで学習した学生は短期的な『覚える』記憶、小冊子は長期的な『知る』記憶と、学習する分には、小冊子の方が身につきやすい結果となりました。(Kate Garland &Jan Noyes 2003)
記憶の種類には、短期記憶と長期記憶がありますが、モニターでの学習は短期記憶、小冊子での学習は長期記憶に向いていることが示唆されています。
『情報』として見る分では、電子書籍のようなディスプレイ型でも問題ないですが、『知識』を得たいなら紙媒体の本が良いということになります。
ただ、実験に使われたモニターはパソコンのため、電子書籍を読むのがパソコンではなくタブレットやスマホだった場合、また違った結果が出る可能性も考えられます。
電子書籍を読むと睡眠の質が下がり記憶が低下する
ハーバード大学医学部のチームは、寝る前に紙の本と発光電子書籍リーダーを読むことを比較しました。
彼らは、バックライト付きの電子書籍リーダーでうなずくのに時間がかかり、その結果、睡眠の質が低下し、翌朝の疲労感が増したことを発見しました。
上記の2014年にBBC(英国放送協会)のネットメディアに掲載されたハーバード大学医学部チームの研究は、寝る前に紙媒体の本と電子書籍を読み、睡眠の比較をした研究です。
ハーバード大学は、世界的に有名な大学で『世界大学ランキング』の1位の常連で、世界有数の名門大学です。
12人の人々を2週間拘束して採血した結果、電子書籍を読んだ場合は睡眠と関わりの深いホルモン・メラトニンが減少し、眠るのに時間がかかり、睡眠の質も悪く疲れた状態でした。
睡眠不足は、記憶を司る脳の海馬に悪い影響があり、記憶力低下に繋がります。そのため、頭に入らない原因になります。
ただ、この研究結果は夜寝る前の話なので、電子書籍を読む時間帯など改善可能な要素があります。
電子書籍のスクロールは触覚によるサポートが弱い
2014年にイギリスの新聞社ガーディアンのネットメディアに掲載された、ノルウェーのスタヴァンゲル大学の研究者アン・マンゲンの研究内容では、スクロールで特定の情報を入手するのは難しいという結果があります。
50人の被験者の半分に電子書籍の短編小説を読んでもらい、もう半分に紙媒体の短編小説を読んでもらい、重要なシーンをどれくらい思いだせるかをテストしました。
結果は、電子書籍で読んだ人は、シーンを正しい順番に並べるテストで、悪い成績となったのです。
この研究からマンゲン氏は、「物語の進行に合わせて紙をめくっていくという作業が、一種の感覚的な補助となります。すなわち、触覚が、視覚をサポートするのです」と述べています。
特定の情報を入手する際は、紙の場合だと紙をめくることで覚えることができますが、電子書籍の場合だとスクロールしなければいけません。
この差が、記憶に残りにくい原因となります。
研究以外に電子書籍が記憶に残りにくいと考えられる要因
研究結果以外にも、電子書籍が記憶に残りにくいと考えられる要因を2つお伝えします。
端末の要因、コスト感覚の希薄化といった電子書籍ならではの要素が記憶の定着を妨げている可能性があります。
アプリなどの通知に邪魔され集中しづらい
あなたのタブレット・スマホには、電子書籍アプリ以外にも他のアプリが入っているのではないでしょうか?
アプリの多くは通知機能がついており、全て通知OFFにしていない限り、電子書籍を読んでる際に他のアプリの通知が入る可能性があります。
本を読んでいて重要な部分で、通知が入ると気が散ります。
記憶に必要なのは『集中力』なので、通知により集中力も低下すると、頭に入らない可能性が高まります。
お金を払った感覚が薄く費用回収に真剣になりにくい
電子書籍は、オンライン上で欲しいと思ったときにすぐ決済できますが、実際に書店に足を運ばす、お財布からお金を出す行動もありません。
書店に行くために時間的なコストが必要なく、お金を払ったという感覚も湧きにくいため、支払った費用を回収しようと行動するパワーが弱まる可能性があります。
結果、本を真剣に読む際の集中力や、学習意欲が低くなり、記憶に残りにくくなる可能性があります。
電子書籍が頭に入らない原因を改善しよう
電子書籍が記憶に残りにくい原因や、頭に入らない原因を紹介してきましたが、ここでは改善を説明していきます。
「改善って、有名な大学の研究結果なのに改善できるの?」と感じるかもしれませんが、原因を分析して対策することで、改善は可能です。
工夫することで、便利な電子書籍のメリットを活かしつつ、記憶に残せるようにしていきましょう。
寝る1時間前に電子書籍の利用を控える
電子書籍を使用すると、睡眠の質が下るとお伝えしました。
この状況を変える方法として、寝る前1時間前に利用を控える方法があります。
電子書籍を使用する場合、タブレット・スマホを利用しますよね。
タブレットやスマホなどの端末から、発光されるブルーライトは、目を疲れさせる原因になります。
目が疲れた状態で寝てしまうと、睡眠の質を下げてしまうのです。
寝る1時間前に目を休めることで、睡眠の質を向上させられますので、実践してみましょう。
それでも寝る時間を惜しんで電子書籍を読みたい方は、目に優しいタブレットを使う方法もあります。

アプリの通知を見直す
集中力を低下させるアプリの通知を見直すことで、頭に入りやすくなります。
通知の設定は端末によって違ってきますが、特定のアプリの通知をオフすることが可能です。
- Android端末の場合・・・設定→アプリと通知
- Apple端末の場合・・・設定→通知
こちらを選択すると、導入しているアプリを選択して、通知をオフにできます。
「個別に設定するの面倒くさい」と感じた方は、一括でオフにする方法もあります。
- Android端末の場合・・・サイレントモードを使用する(メーカーで異なります。)
- Apple端末の場合・・・おやすみモードを使用する
この方法を使用すると、個別に通知がオンになっていても、通知はきません。
設定画面から登録もできますが、トップ画面から上下などでスワイプすると、
- Android端末の場合・・・クイック設定パネル
- Apple端末の場合・・・コントロールセンター
が表示されますので、そこでも変更は可能です。
「これだけは、通知がきてほしい!」と思われる方は、個別で通知をオフ。
「読書に集中したい!」「勉強する!」という方は一括で通知をオフにする方法がおすすめです。
専用端末を利用する
電子書籍専用の端末は、タブレット・スマホに比べ、頭に入りやすくなることができます。
理由は以下の通りになります。
- ブルーライトの発光が少ない
- 他のアプリを入れることがないので、通知がこない
- 読書時間にしか使用しないため、読書する気持ちにスイッチできる
などがあげられます。
専用端末を使用することで、『頭に入らない』といわれる電子書籍への対策ができます。
専用端末もストアによって、色々ありますので、あなたに合ったものを選びましょう。
電子書籍の利用に慣れる
電子書籍を読む際にスクロールなど行いますが、紙媒体の本を読んでる人が使用すると、慣れていないのでストレスを感じたりしませんか?
記憶する、頭に入るようにするためには、読書を楽しむことが大切です。
楽しむことで、興味を持ち、覚えようとします。
最初のうちは慣れずにストレスを感じてしまいますが、慣れてしまえば、紙媒体の本同様に楽しむことができます。
時間はかかりますが、慣れることで記憶に残りやすくなるので、試してみましょう。
電子書籍の読書術を習得して記憶に残す方法
ここまで、電子書籍が『記憶に残りにくい』『頭に入らない』原因と改善を説明してきました。
それでも、「まったく、頭に入る気がしない」と感じているかもしれません。
そう感じる方は『読書術』を学ぶことで、記憶の向上をさせるのも1つの方法です。
『記憶に残りにくい』『頭に入らない』など悩んでる方は、実践することで変わってきます。ぜひ、取り組んでみて下さい。
目次を見て本文を予想する
記憶に残る、頭に入るためには、読んでいる本に興味がないと始まりません。「この本面白い!」「この表紙素敵!」などと感じる本を読むことが大切です。
本を買っている時点で、興味を持っている本であることは間違いないはずですが、より関心を高めるために、本を読む前にできることをお伝えします。
それは『目次を見て本文を予想すること』です。
まず、本文を読む前に目次に対して、自分なりにどんな本文が書かれているのかを、予想して下さい。
それにより、自分が予想した内容と本文が正しいのか、それとも違っているのか、興味・関心が増します。
実際に読んだときに「やっぱり自分の予想通りか」「こんな展開だったとは」など感じることで、ゲーム感覚で記憶の定着力を上げられます。
本文を読む前に実践することで、頭に入りやすくなるので、ぜひ実行してみて下さい。
スクショ機能を使って覚えたい項目をデータ化する
『記憶に残りにくい』『頭に入らない』状態は、読み返して復習することで改善されます。
復習の際に覚えたい部分を探すためには、スクロールする手間が発生しますが、電子書籍タブレットやスマホの『スクショ機能』を使い、覚えたい項目をデータ化することで復習を効率化できます。
電子書籍の画面をスクショする方法は以下の通りです。
- Android端末の場合・・・電源ボタンと音量小ボタンを長押しする。
- Apple端末の場合・・・サイドボタンとホームボタンを同時に押す。
操作方法も簡単で、電子書籍の画面をスクショできます。ぜひ活用しみましょう。
読み上げ機能を使い音声を聞いて覚える
電子書籍の内容を覚える方法には、見て覚える、読んで覚える以外にも、聞いて覚える方法があります。
スマホやタブレット・専用端末には『読み上げ機能』が存在し、電子書籍の文面を声で読み上げてくれるのです。
「読んでて目が疲れた」「文章が苦手」という方は、読み上げ機能を使って、学習をしてみましょう。
また、睡眠学習に利用することで、さらに記憶に残りやすくなります。
読み上げ機能のやり方は以下の手順でできます。
- 設定を選択
- ユーザー補助>TalkBackを選択
- TalkBackをオンにする
- 電子書籍を開く
- 音量の上下ボタンを押し読み上げ開始
TalkBackをオンにすると突如画面を読み上げるため、音量に注意して下さい。
※Android端末の中にはTalkBackが入っていないことがあります。
その場合はGoogle Playでダウンロードできますので、利用しましょう。
- 設定を選択
- 一般>アクセシビリティ>スピーチ>画面の読み上げの順番で選択
- 画面の読み上げをオンにする
- 電子書籍を開く
- 画面上から下に2本指でスワイプ
- 読み上げメニューが表示され読み上げを始めます
以上のやり方で、読み上げができるようになります。
慣れれば面倒に感じなくなりますので、活用して読書の効率化を上げていきましょう。
より詳細に知りたい方は、『電子書籍読み上げの設定方法』も合わせてご覧ください。

電子書籍の記憶はやり方次第で頭に入ります(まとめ)
電子書籍の『記憶に残りにくい』『頭に入らない』はやり方次第では、変わってきます。
電子書籍と紙媒体の本の比較と研究は、今でもされていますが、それ以上に原因を解決するための『進化』もしてきているのです。
専用端末の開発、読み上げ機能の追加などは、研究結果からの対策から生まれた機能の1つだと考えられます。
また、何事にも問題はつきものです。それに対して、プラス何をするのかを考えることが大切なのではないでしょうか?
この記事では『記憶に残りにくい』『頭に入らない』について原因・改善方法・記憶定着向上方法などをお伝えしてきました。
本記事が少しでも電子書籍の『記憶に残りにくい』を打破するお役に立てれば嬉しい限りです。


2003年のKate Garland氏とJan Noyes氏の研究全文 https://www.researchgate.net/publication/223454988_VDT_versus_paper-based_text_Reply_to_Mayes_Sims_and_Koonce